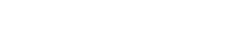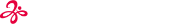人力車 くるま屋
浅草は、浅草寺、仲見世などの観光地や、どぜう鍋やすき焼き、天丼などの和食グルメ等、 江戸文化や下町情緒が今でも残っているのが大きな魅力の一つであるが、 その一端を担っている一つに人力車のある風景がある。
今回は、俥夫であり人力車会社「くるま屋」の経営者である三浦翔平氏に話を伺った。

氏は「人力車 くるま屋」を始めるまでに消防士と海上保安庁職員という、 人命救助のスペシャリストとして働いていた。 高校二年生の時に東日本大震災を経験し、
テレビに映る被災地に対する無力感を感じるとともに、そこに映った懸命に働く消防士の姿に憧れ消防士を志す。
二年間消防士として充実した毎日を送っていたが、
休暇で訪れたバリ島で貧しい子供等の姿を目の当たりにし、
この現状にどうにか自分が力になれることはないかと帰りの飛行機で考え、
その足で職場に退職を宣言し海上保安庁で働く決意をする。
厳しい試験も二回目で突破し念願の海上保安庁職員となるが、働いてみると秒単位で管理される規律の厳しさや、自身が持っていたイメージとは違った環境に初めての挫折を経験し、退職を選択することとなる。
挫折に苦しみ、半年間引きこもりの生活を送るが、
実家に身を寄せながらも、家族ともほとんど顔を合わせない生活を送った。
ある日、心配した母とたまたま会話することがあり、怒られるかと身構えていた氏だが、
思わぬ言葉をかけられた。
「あなたは今まで素晴らしい仕事をしてきたのだから、今度はもっと人生を楽しみなさい」
この言葉に奮起し、その時部屋のテレビに偶然映っていた雷門を走る人力車を指差し、
「これでもやるよ」と宣言する。どうにか引きこもりの生活を脱しようとした第一歩である。
これがきっかけで現在のくるま屋まで続く人力車人生が始まったのである。
俥夫をやる中での一番の喜びはお客さんの笑顔だったという。
初めて人力車を曳いた時のエピソードを伺った際は、頭が真っ白で何も覚えていなかったそうだが、
乗せた親子の笑顔だけは忘れられないとおっしゃっていたのが印象的だ。
ある日、SNS 上にて昔の上司から 「人命救助から人生救助だな」とのコメントが残されていた。
氏が人命救助に心血を注いでいた時代と人々の喜びのために汗を流す現在が繋がった瞬間であった。
人を喜ばせたいとの想いがここまで氏を走らせてきたのである。
氏の言葉の中でも特に興味深かったのは、人力車の歴史の語り部としての存在意義についてである。
人力車は明治時代初期に普及し庶民の足として東京中を走っており、文明開化の象徴ともされていたが、
現代において純粋な移動手段として使う人はほとんどいないであろう。
それが今でも残っているのはその土地の語り部としての存在が大きい。
浅草を拠点に活躍するくるま屋をはじめとする人力車の俥夫たちは、浅草のことを語る時、
隅田川から両国橋の歴史、浮世絵のモチーフなどを通して現在の浅草の枠を超えて
両国など他地域へと広がっていく。
私たちはこの語りを通して現代の浅草、東京、日本から
かつてあった江戸文化へと思いを馳せることができるのである。

氏はくるま屋を立ち上げる際に、2 つのことを目標に掲げていた。 一つは人の思い出を作りに携わる。 これはシングルマザーであった氏の母が、多忙の中週末ごとに遊びに連れて行ってくれた記憶が 自分にとって大きな支えになったため、他の人にとっての浅草観光も素敵な思い出にしていきたいとの 思いからである。
二つ目は「若者を照らす」ということである。
これは自身が若い時に挫折し進む道がわからなくなった時、人力車が自身の新たな道へ進む道標と
なったことから、同じように悩んでいる若者の飛躍の出発点でありたいとの思いから来ている。
実際にくるま屋に在籍している俥夫は若い人が多い。
先日も俥夫をしている大学生が、くるま屋で働く中で、自分の長所は海外の方を喜ばせる力だと気づき、
自らインバウンド向けのツアー会社を立ち上げたというエピソードを伺った。
氏の、自分のことのように喜んでいる姿が印象的であった。

自らを飽き性だと自認している氏がここまで人力車を続けてこられているのは、
学びに終わりがないからだという。
接客の仕方やガイドの知識量、人力車を引く速度まで、
何百と同じコースを走っても学ぶことが尽きないそうだ。
第一ホテル両国と提携するとのことで、
今一度両国の歴史を学ぶ中で、その魅力にワクワクしていると話す氏とくるま屋の新たな語りを
楽しみに待ちたい。